経済的に困っている人で、生活保護を受ける前の手段の一つとして、個人信用情報機関に信用情報を照会審査なしで、超ブラックにでも無利子または低金利でお金を借りれる「生活福祉資金貸付制度」という法律で決められた公的な援助金があります。
- 「仕事がみつからない」
- 「社会に出るのが不安」
- 「失業して家賃が払えず、家を追い出されそう」
など、さまざまな困難な中で、生活に困窮している人に包括的な支援を行う制度です。
国の制度なので、貸付条件に当てはまれば誰でも貸してもらえるのですが、社会福祉協議会が窓口となって審査していますので、担当者次第では審査に落ちたという話もあります。
信用情報で審査しない生活福祉資金貸付制度とは
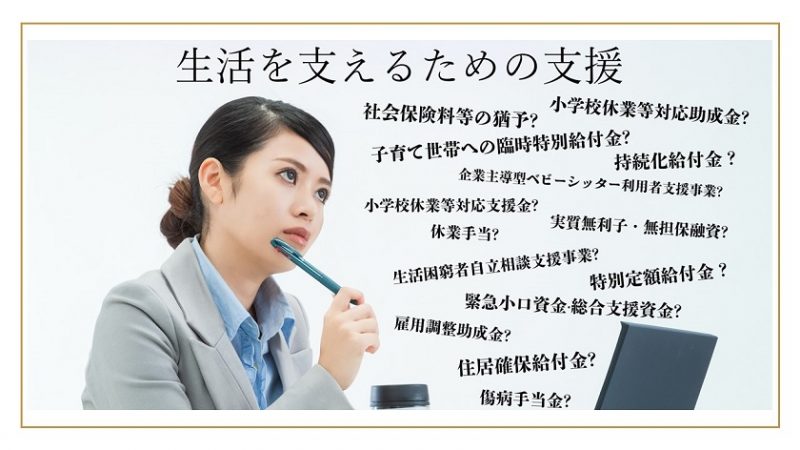
生活福祉資金貸付制度とは、年金や医療保険などのセーフティーネットに対し、「第2のセーフティーネット」と言われており、個人信用情報機関の信用情報を照会せずに審査しますので、ブラックでも借りれるのです。
「最後のセーフティーネット」の生活保護の手前で困窮者を支える狙いで、2015年4月に始まりました。
自治体は窓口を設け、専門の担当者が一人ひとりの支援計画を作成します。就労支援や子どもの学習支援のほか、就職活動を条件に家賃を支給する仕組みもあります。事業の多くは任意で、自治体によって差があります。
どんな人が支援の対象?
たとえば・・・
- 生活に困っている
- 仕事をリストラされてどうしていいかわからない
- 失業して家賃が払えない
- 仕事がみつからない
- 住むところがない
- ずっと家にいたから社会にでるのが不安
- 家族がひきこもっていて、相談できる人がいない。
などの方が対象になります。(生活保護を受給されている方は除きます)
本人だけではなく、家族やまわりの人からの相談も社会福祉協議会で受け付けています。
相談は無料で、秘密も守られますので安心して相談ください。
生活福祉資金貸付の種類
生活福祉資金貸付の「総合支援資金」は、「総合支援資金」は、失業などによって生活に困窮している人が、生活を立て直し、経済的な自立を図れるようにするために、社会福祉協議会とハローワークなどによる支援を受けながら、社会福祉協議会から、生活支援費や住宅入居費、一時生活再建費などの貸付けを受けられる貸付制度です。
生活支援費
生活支援費は、生活を再建するまでの間に必要な生活費として、月20万円までの貸付けを最長12か月間行うものです(単身世帯の場合は月15万円以内)。
住宅入居費
住宅入居費は、敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な資金として、40万円までの貸付けを行います。
一時生活再建費
一時生活再建費は、就職活動や技能習得、家賃や公共料金などの滞納の一時立て替え、債務整理に必要な費用などについて、60万円までの貸付けを行います。
これらの資金は、連帯保証人なしでも貸付けを受けることができます。なお、貸付利子は連帯保証人がいる場合は無利子、連帯保証人がいない場合は年1.5%になります。
「総合支援資金」の貸付対象者は
総合支援資金の貸付対象となるのは、貸付けを行うことにより自立が見込まれる方で、下記の要件のいずれにも該当する人です。
- 低所得者世帯(市町村民税非課税程度)で、失業や収入の減少などによって生活に困窮していること
- 公的な書類などで本人確認が可能であること
- 現在住居のある人、または、住宅手当の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること
- 社会福祉協議会とハローワークなど関係機関から、継続的な支援を受けることに同意していること
- 社会福祉協議会などが貸け付及び支援を行うことにより、自立した生活を営むことが可能となり、償還を見込めること
- 他の公的給付または公的な貸付けを受けることができず、生活費をまかなうことができないこと
生活福祉資金貸付制度の総合支援資金の貸付けを申し込むには
離職されている方が、生活福祉資金貸付制度の総合支援資金を利用するには、まず、ハローワークへの求職申し込みと職業相談が必要です。まずは、ハローワークで求職登録を行ってください。
また、総合支援資金は原則として住居がある人を対象にしており、住居がない人は、地方自治体で実施している住宅手当の申請を行い、今後住居の確保が確実に見込まれていることが条件となります。
住居がない人は、総合支援資金の申し込みをする前に、これから入居を予定している地域の自治体で、住宅手当の相談をしてください。
総合支援資金の相談・手続きの窓口は、市区町村の社会福祉協議会です。窓口で手続きの説明と用紙の交付を受けた後、申請書に下記の書類を添えて提出してください。
審査の結果、貸付けが決定されると、住宅入居費の貸付金は家主・不動産業者などの口座へ、それ以外の貸付金は本人の口座に振り込まれます。
総合支援資金申請から融資されるまでの流れ
- 借入申込書
- 借用書
- 収入の減少状況に関する申立書
- 口座振替申請書(返済時の口座登録)
- その他必要書類
貸付審査には、民生委員、社会福祉協議会による調査がありますが、信用情報機関に登録された情報は取得できません。
承認通知が届けば、ご自身の指定金融機関に振り込まれます。
- 総合支援資金の借入申込書
(社会福祉協議会の窓口で交付します) - 健康保険証または住民票の写し
- 世帯の状況が明らかになる書類
- 連帯保証人の資力が明らかになる書類
- 求職活動などの自立に向けた取り組みについての計画書
- 借入申込者が、他の公的給付制度または公的貸付制度を利用している場合、または申請している場合は、その状況が分かる書類(ハローワークが発行します)
- 借入申込者の個人情報を、総合支援資金の貸し付けに必要な範囲において関係機関に提供することについて記載されている同意書
- 住宅入居費の借り入れを申し込む場合の添付資料
①入居する住宅の不動産賃貸契約書の写し
②不動産業者の発行する「入居予定住宅に関する状況通知書」の写し
③自治体の発行する「住宅手当支給対象者証明書」 - 総合支援資金の借用書
- その他、社会福祉協議会が必要とする書類
審査等は厳しいと言われる制度ですが、条件を満たせそうであればまず相談し、生活保護を受給することも考えてみましょう。
貸付開始までの間の生活費を支援する「臨時特例つなぎ資金貸付」
失業など給付や住宅手当などの離職者を、支援するための公的給付制度または公的貸付制度を申請している住居のない離職者のうち、給付・貸付けが開始されるまでの間、当面の生活費の支援を必要とする人は、「臨時特例つなぎ資金貸付」を活用することもできます。
これは、10万円までの資金を、連帯保証人なしで、無利子で貸し付けるものです。申請窓口は現在お住まいの住所を管轄している市町村の社会福祉協議会になります。
住居確保給付金について
住居確保給付金は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第5条に基づき、離職又は自営業の廃業(以下「離職等」という。)により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。
- 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがあること。
- 申請日において65歳未満であって、かつ、離職等の日から2年以内であること。
- 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた方であること。
- 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額(※)」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。
(※)「基準額」とは、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12をいいます。 - 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額の6倍(ただし100万円が上限)以下であること。
- 公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。)に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
- 国の雇用施策による職業訓練受講給付金又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと。
支給額
月ごとに家賃額(生活保護法に基づく住宅扶助の限度額が上限)を支給します。ただし、世帯の収入合計額が基準を超える場合は、一部支給となります。
支給期間
原則3ヶ月間で、誠実かつ熱心に求職活動を行っている等、一定の要件を満たす場合には、申請により3ヶ月間を限度に支給期間を2回まで延長することができます(最長9ヶ月間)。
支給方法
住宅の貸主(大家)の口座へ直接振り込まれます。
申請窓口
申請窓口は現在お住まいの住所を管轄している市町村の社会福祉協議会になります。
都道府県・指定都市社会福祉協議会はこちら
受給中の求職活動について
住居確保給付金受給中は、上記の自立相談支援機関の就労支援やハローワークの利用等により、常用就職に向けた次の求職活動をする必要があります。
- 月4回以上、自立相談支援機関等の就労支援を受けること。
- 月2回以上、ハローワークで職業相談を受けること。
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
最後に
日本にはあまり知名度や認知度は高くなくても様々な総合支援資金のような福祉の救済制度があり、条件をしっかりと満たしている場合は誰でも利用する事が出来、もちろんそれはけして恥ずかしい事ではありません。
人生を自力で生きていくため、大事な家族を守るために必要な場合は貸付の審査の手続きを行いましょう。
基本的にどんなに強い人間でも困っている時は冷静な判断をする事が難しい状態に陥ってしまっています。
社会福祉協議会や市区町村の担当の方と話をする事で自分だけでは見えなかった解決策を発見できる事もあります。
また誰かに相談できる事で落ち着いて行動できるようになる事もありますし、関連記事「スーパーブラックでも借りれるのは消費者金融だけじゃない!」も参考になると思います。









